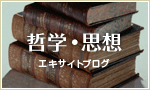精神との関係の巻
<姿勢は、矯正。精神は、作られるイメージで、姿勢の緊張感によって、影響も受けている>
いつの間にか丸まってる背中。子供の頃から、姿勢悪いなって思っていて、大人になっても変わらず姿勢って悪いまま。これはいかんとピシッと伸ばす背筋、でも15分くらいすると、また丸まってる。今日はそんな姿勢の話。精神・・・・・・・・・・・・・・
精神と近しい。姿勢と精神はなんとなく近しく感じる。どうして近しく感じるのかを、今日は探って行きたい。姿勢というのは体で、精神というのは概念。どうして姿勢と精神を、近しく感じるのだろう。態度・・・・・・・・・・・
態度は心。例えば態度って言うのは、そのヒトの心を表す。ふんぞり返っている人、うつむいている人、だらけている人、堂々としている人。心の持ちようを、体は態度というカタチで、見事に表している。態度と姿勢・・・・・・・・・・
態度と姿勢はほぼ同じ。いきなり核心に近づいてしまった。ちょっと展開が早いが、態度と姿勢はほぼ同じ意味合いで、精神と心も非常に似ている。とすると、体に表れるモノは、見えないハズの心の中も見せてくれているという事か。逆に・・・・・・・・・・・
逆に体。カラダの方を変えるコトで、心の持ちようも変えるコトは可能だろうか。姿勢を良くする事で、心持ちを変えられるのか。姿勢を正すと、確かに気持ちまで張り詰めた感じになる。やっぱりそうだ!逆もアリなんだ。密接・・・・・・・・・・・・
密接に関わっている。どうやら、体と心の中は密接に関わっていて、影響し合っている事が分かる。それはひとつの結論として、納めても良いと思う。さて、では精神と姿勢についてもう少し。精神・・・・・・・・・・・・・
そもそも精神って。姿勢は分かるけど、精神というモノがなんなのか、分かるようで実は漠然としている。先ほどの張り詰めた感じというのが、何らかの手がかりになると思うのだけれど、そこら辺をちょっくら探ってみる。弛む・・・・・・・・・・・
精神が弛む。どうも、精神が弛むというのは、シックリ来ない。張り詰めるに感じるモノがあったので、逆の状態である弛むを当てはめてみたのだけど。どうも違うらしい。さて、精神というモノは一体何なのだろうか。精神力・・・・・・・・・・・・・
精神力という言葉。精神力が強ければ、苦難があってもすぐに立ち直れる。精神力が弱いと、少しの事でもくじけてしまう。この二つの違いをヒントに、精神というモノがなんなのかを、突き詰めたい。行動・・・・・・・・・・・・・・・
立ち直るもくじけるも、行動。精神力が強いと弱いとで、ナニが違ってくるかといえば行動。ただ、ちょっと待って欲しい。行動の前には、頭の中である程度想定する。そうか、どちらかと言えば行動よりその前。プログラミング・・・・・・・・・・・・・・
行動前のプログラミング。行動する前には、頭の中のプログラミングがいろいろ想定している。このプログラミングに影響しているのではないか。精神というのは、行動を決める想定に強く影響している。行動の選択肢を、頭のプログラミングがたえず決めている。積極性・・・・・・・・・・・・・
積極性と、消極性。行動が、積極的か消極的かを、精神が決めているのだろうか。その可能性は高い。その先で困難を乗り越えられると思えば、積極的になるし、逆なら消極的。それこそ精神力と同じモノ。経験・・・・・・・・・・・・
過去の経験。もしも、過去に乗り越えられた経験があれば、積極的に挑戦出来る。精神力は生まれつきのモノではなく、経験によっても変わるモノ。そういって間違いないような気がする。記憶・・・・・・・・・・・・・・
では記憶だろうか。精神力に影響するのは、記憶で間違いないように思う。積極性や消極性は、記憶の賜物で、それは精神力の示す意味とも直結する。ただ精神力なら良いが、チカラを取り除いた精神と言う言葉になると、どうも記憶とに違和感を感じる。ナニかが違うような気がする。一体なぜそう思ってしまうのか。勘違い・・・・・・・・・・・・
精神自体が、勘違い。ここで一つ、とんでもないコトが思い浮かんでしまった。こんなコトを言うと、頭がオカシイと思われるだろうが、実際頭がオカシイので続けさせて貰う。そのとんでもないコトとは、精神なんて無いというコト。作られる・・・・・・・・・・・・・・
作られるイメージ。精神などと言うモノは無く、記憶から作られるイメージではないだろうか。それで、乗り越えられた記憶を持つヒトは、積極的になるだろうし、挫折ばかりの人は消極的になる。これは全て記憶の成せる業。赤ちゃん・・・・・・・・・・・・・・
赤ちゃんに精神はあるのか。赤ちゃんや子供という、経験の少ない状態で、精神はあり得るだろうか。欲望に対して耐えるチカラなど、子供でも個性はあるように思う。それは精神と言えなくもない。でも同時にそれは、作られるイメージとも言えるのではないか。理由・・・・・・・・・・・・
理由がある。なぜその欲望に耐えられるか。例えばお菓子が食べたいが、お母さんにダメだと言われている。このダメだと言われているのが理由。理由があるから耐えられる。理由という点では、作られたイメージの方も、過去の記憶がそれににあたる。沿う・・・・・・・・・・・・・
理由に沿う。経験の少ない子供も、理由に沿って行動を決めている。言われたからか、記憶かの違いだけで、理由があるのは同じ。行動を決めるという点で、作られるイメージも精神も同じ。この二つを置き換えても、不具合は出ない。精神を、作られるイメージに置き換えても、なんら矛盾はないという事。決まり・・・・・・・・・・・
これに決まり。精神というのは、作られるイメージと言うコトを、私なりの解としたい。精神が、記憶などの理由による、作られるイ
メージというのは意外だったが、それを私の答えとする。戻る・・・・・・・・・・・・・
最初に戻る。精神の答えが出た所で、最初に戻って姿勢との関係を考えてみたい。精神が、作られるイメージとすると、お互いに関係し合っている姿勢は、どういう位置づけになるのだろうか。緊張感・・・・・・・・・・・・・
姿勢の緊張感。張り詰めた感じと言う表現は前述した通り、これに通じるモノとして、姿勢を正すと緊張感が増す。ここが大いに関係するような気がする。怪しい匂いがプンプン。探ってみよう。与える・・・・・・・・・・・
影響を与える。姿勢の緊張感が、作られるイメージに影響を与えるのではないだろうか。もしそうだとして、何に影響を与えるのだろう。記憶によって作られるイメージの何に影響を与えるのか。未来像・・・・・・・・・・
イメージは未来像。なぜイメージをするかと言えば、行動をする前にあらかじめ想定するから。未来を緊張感を持って矯正する。イメージは作られるモノだから、姿勢の緊張感によって矯正されても不思議ではない。スッキリ・・・・・・・・・
自分の中ではとてもスッキリ。姿勢の緊張感で、イメージが矯正される。これを、わたしなりの結論としましょう。いろいろ紆余曲折あったけど、スッキリする答えまで辿り着けましたね。それじゃ締めましょう
姿勢は、矯正。精神は、作られるイメージで、姿勢の緊張感によって、影響も受けている
ひゃ〜!精神って言うのは、脳のイメージ。記憶とかによって、これからの行動を想定する時に、影響するイメージだったとは。精神てモノ自体無かったとは意外や意外。自分でも驚きですよ。いや〜参った参った。そして姿勢は、そのイメージに緊張感を与えて、矯正してるなんてね。自分でやってて、なるほどなるほどです。はい。それじゃ明日ね
明日は『ポジティブ』というタイトルで、本当に追い込まれるについて考えます。お楽しみに!!