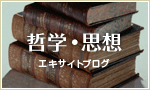噛み合わないの巻

<教育論議は、○○○○○。○○○○を育てる方向性と、全員○○○ようにする方向性。まるで違う○○に向かって話し合われるので、噛み合うワケがない>
昨日のブログでは、二つの大きな流れがあってその二つの流れが分かると、教育というモノの本質も見えるんではないかという内容でした。では、さっそくその二つの流れがなんなのか、解答編をスタートさせましょう。とっぷ・・・・・・・・・・
トップの子。勉強ができるトップの子を見る人。日本人として誇れるトップの子にスポットを当てて、教育を論じる人がいる。トップの子は勉強ができる、いわゆるエリート。「どうやったら優れた子供になれるかって言う、分かり易い考え方だね。」こくさい・・・・・・・・
国際的評価。トップの子を見る人は、国際的評価の話を持ってくる。気にするコトは、どれだけ優れているか。世界的に見て優秀であれば安心するし、劣等なら不安になる。「日本人が優れていないってコトになったら、腹立たしく思う人達だね。」かち・・・・・・・・・・
勝ち負け。教育を勝ち負けと捉えている。トップの子供にスポットを当てている人は、教育を勝ち負けで捉えている。国際的な場でも勝ちたくて、自国が優れているコトを示したい。「世の中は勝ち負け多いし、単純で分かり易いから、そこに重点を置くんだね。」ぼとむ・・・・・・・・・・
ボトムの子。勉強ができないボトムの子を見る人。いわゆる底辺の子を見て、教育を論じる人も居る。苦手だったり、うまくいかない子の方に重点を置く。「出来ないからと切り捨てるんじゃなくて、どうにかするべきだと思う人達だね。」こぼす・・・・・・・・・
取りこぼす。全員出来るようにしたいのに、取りこぼす。どんな教師でも、全員出来るようにしたい。ただ現実は出来ないまま次の学年に送っている。つまり取りこぼしをしている。「全員出来るようにというのは、現実にはどの先生も出来ていない。つまりどの先生も取りこぼしているわけだね。」ざいあく・・・・・・・・・・・・
罪悪感。取りこぼしによる罪悪感。どの先生も、取りこぼしている事実を、多かれ少なかれ感じている。その罪悪感から、何とか制度を改善したいと願う存在。「努力しても取りこぼしてしまうのは、制度自体が問題だから、それを改善したいってコトだね。」ふたつ・・・・・・・・・・・
二つの流れ。これは目的が違っているので、二つの流れになる。一つはエリートを育てる。もう一つは全員出来る。目的が違っている為に、教育論議は噛み合わないコトが多い。「教育に対する考えをぶつけ合わせても、目的が違うから、どうもまともにぶつからないんだよね。」えりーと・・・・・・・・・・・・・・・
エリートを育てる。教育の目的がエリートを育てるだった場合。エリートを育てさえすれば、あとはどうでもイイから、出来ない子を切り捨てても問題にはならない。「国際的に見て、自国の子供が優れていれば良いワケだから、出来ない子は見なくても良いんだね。」はーどる・・・・・・・・・・
ハードルを上げる。優れた子を育てる為に、ハードルを上げる。ハードルを上げるほど、エリートは鍛えられ有能になる。同時について行けない子も増え、切り捨てられる子も増加する。「自国が他の国に負けないように、どんどんハードルあげて優れた子を出そうってコトだけど、切り捨ても横行するワケね。」へんしつ・・・・・・・・・
変質する。ハードルを上げても変質する。優れた子を育てるつもりが、どうもそうならない。ハードルを上げるほどに、点数を取る能力は増していく。でも、有能な子が増えるかと言えば少し違う。「目的は優れた子を育てるだけど、ハードルあげてもそうならないのか。」とっか・・・・・・・・・・・・
特化する。点数を取るコトに特化する。優れた子を育てるつもりが、点数を取るコトに特化した子を育ててしまう結果になる。あまりに優れた子を育てようとしすぎて、本質からズレているのにも気づかなくなる。「点数取っていれば安心してその結果を受け入れるけど、点数を取るコトと優れているコトはズレがあるんだね。」あんい・・・・・・・・・・
もともと安易。勝ち負けで見るのはもともと安易。とても分かり易いけど、それだけに中身を見ていない。結果だけを見て判断してしまっている。ズレに気づかないのも中身を見ていないのが原因。「良い結果が出ている内は、疑う事もしないかもね。」ずっと・・・・・・・・
ずっと同じ。教育はずっと同じ、エリートを育てる流れ。日本に来る前から、教育はエリートを育てる流れにある。全員出来るようにするというのは、従来からの流れに反する行為。「勝ち負けだったり、エリート育てる流れって言うのが本流ってコトか。」まだ・・・・・・・・・・・・・
まだない。全員が出来るようになった事は、まだない。出来ない子にスポットを当てて、出来るようにする流れ。ただ、それが出来た事は一度もなく、研究も進んでいない。「対立はしてるけど、圧倒的にエリートを育てる方が強いってコトだね。」むずかしい・・・・・・・・・・
とても難しい。安易な勝ち負けと違って、とても難しい。学校で全員が出来るようになるのはとても難しい。それでまるで進まない。対立していても、結局今まで通り。「何とかしようとする気持ちはあるけど、実体が伴っていないんだね。」うけいれる・・・・・・・・・・・・
取りこぼしを受け入れる。教師にとって、自分の取りこぼしを受け入れるコト自体難しい。取りこぼしは、教える能力が未熟であると認めるコト。そんな事実からは誰でも逃げたい。それも改善が進まない理
由。「自分が悪いなんて誰も認めたくないから、ほとんどの教師は逃げちゃうんだよね。」めいそう・・・・・・・・・・・
迷走する。教育論議は迷走する。噛み合わないだけでなく、対立する側がまだ不十分な体制なので迷走する。それぞれの思惑と、事情が絡み合って教育の論議は何一つ進まない。それが現状。問題がありながら、話し合いの段階にも関わらず、何も進まない。本当に変わるようになるのは相当先なのに、その一歩目も危うい。本当に困った事だけど、それが現状。教育が実質的に改善されるのはいつなんだろう?少なくとも、教育論議が噛み合わないのは、別の目的で話し合いをしているのが理由。というコトだけを、今日のまとめとしましょう
教育論議は、噛み合わない。エリートを育てる方向性と、全員出来るようにする方向性。まるで違う目的に向かって話し合われるので、噛み合うワケがない
別の目的かぁ。二つの流れは、トップを見るかボトムを見るか。この上流と底辺て、社会の中での問題に近いのかもしれない。人間の社会って、どっちを見るかでまるで違う。だいたい上流ばかり有利に働いて、底辺にはしわ寄せがいく。でも上流も結果ばかり見て、中身を見なくなるとズレておかしくなる。なんだろうね、今日は教育だけの話なのに、世の中の問題に置き換えても通用してしまうとは。不思議なもんです。それでは明日に繫ぎましょう
今日もこのブログをご覧頂きありがとうございます。今日は、教育がエリート指向と取りこぼしのないようにする、この二つの目的で成り立っているという内容でした。テレビなどで教育の事がテーマになったら、その人がトップとボトムのどちらを見ているかチェックしてみて下さい。それで切り分けると、どこら辺で噛み合わないのかが明確になると思います。それでは次回をお楽しみに!!ありがとうございま〜〜す!!